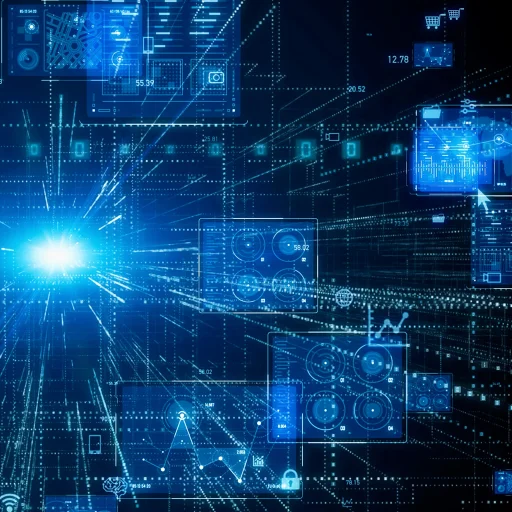概要
令和7年(2025年)6月6日に農林水産省が食料・農業・農村基本計画に基づく研究開発の総合指針「農林水産研究イノベーション戦略2025」(以下「戦略2025」という。)を策定しました。
戦略2025では、新しい食料・農業・農村基本計画に基づき、食料安全保障の強化や環境に調和した食料システムの確立を目指す技術開発を示しており、スマート農業や育種支援システムで生産性向上や品種開発を推進するとともに、国立研究開発法人やスタートアップの支援を強化し、民間主導の研究開発プラットフォームの形成等を進めていくとしています。また、将来の農業経営の姿を技術マップで示しています。
本記事では、戦略 2025の内容を以下にそってポイントをお伝えします。
- スマート農業技術による生産性向上
- 環境にやさしい農業へ
- ICT基盤&データ経営で圃場を見える化
- 現場とともに進む研究へ
農林水産技術マップ(農業版)
スマート農業による生産性向上
日本の農業は、農業者の減少や高齢化により、作業の効率化と省力化が急務となっています。そこで、ロボット・AI・IoTなどの先端技術を活用した「スマート農業」の導入が進められており、農作業の負担軽減だけでなく、農畜産物の品質向上や経営の効率化も実現し、生産性の大きな向上が期待されています。
具体的には、様々な作業に対応できる農業機械や、ドローン・衛星画像を活用した栽培支援アプリ、遠隔操作や自動走行が可能な機械の開発が進んでいます。また、畜産分野でもAIを用いた健康管理や自動給餌機の開発が進行中です。
さらに、スマート農業と相性の良い新品種の開発も重要視されており、多収性や高温耐性、病害虫への強さを持つ品種の育成が行われています。AIやビッグデータを活用して品種改良のスピードと精度を高める「スマート育種」も導入されています。
これらの取り組みにより、地域や気候に応じた持続可能な農業の実現を目指し、農業の未来を支える技術革新が加速しています。
環境にやさしい農業へ
カーボンニュートラルの実現や、化学農薬・化学肥料の使用量削減といった環境負荷の少ない農業を実現するため、環境と調和した新たな技術の開発が進められています。作物や土壌の性質を科学的に分析し、それぞれの特性を最大限に活かすことで、持続可能な農業への転換を目指しています。
まず、カーボンニュートラルの実現に向けては、農業機械の電化・水素化、CO₂を多く吸収する作物の育成、バイオ炭を活用した炭素貯留、温室効果ガスを抑える栽培技術の開発が進行中です。畜産分野では、牛のメタン排出量削減や家畜排せつ物の資源化が課題となっています。
化学農薬の削減では、天敵の活用やレーザー・超音波による害虫防除、作物ウイルスに対するワクチンの大量生産技術など、多面的な総合防除(IPM)技術の導入が進んでいます。
さらに化学肥料の削減に向けては、下水汚泥など未利用資源からの肥料成分回収、生物的硝化抑制作物の開発、土壌と微生物の関係を活かした省肥料技術の構築が進められています。
これらの技術を通じて、環境と調和した持続可能な農業への転換が期待されています。
ICT基盤&データ経営で圃場を見える化
農業の高度化に向けては、AIやIoTなどの情報通信技術を活用し、圃場の状況を「見える化」することが不可欠です。全国の圃場データを集約し、ビッグデータとして整備したうえで、APIを通じて誰もが使えるようにすることで、データの利活用を促進します。
さらに、地域や品目ごとに最適な生育・収量予測ができるよう、農業に特化したAIの開発も進められています。また、生成AIや大規模言語モデル(LLM)を活用し、栽培や経営、販売などを支援する機能も研究中です。これらの技術をAPIで公開することで、スタートアップによる生産管理アプリなどの開発も後押しされ、農業の意思決定をより正確かつ効率的に行えるデータ経営の実現が期待されています。
「現場とともに進む研究」へ
農業の研究現場が、今、大きく変わり始めています。農業・食品分野で唯一の総合的な研究機関である農研機構では、老朽化した施設の更新にあわせて、大学や民間企業との連携を前提とした「オープンな研究の場」づくりが進行しており、スタートアップなどによる技術実証の受け入れ体制整備も含め、研究成果を現場で活用する仕組みを強化しています。
また、研究開発成果である知的財産の保護と活用が強化されています。これにより、農林水産分野の競争力が強化され、国際標準化も視野に入れた知財マネジメントが進められています。
これらの取り組みにより、農林水産分野の持続可能な発展と食料安全保障の強化が期待されます。